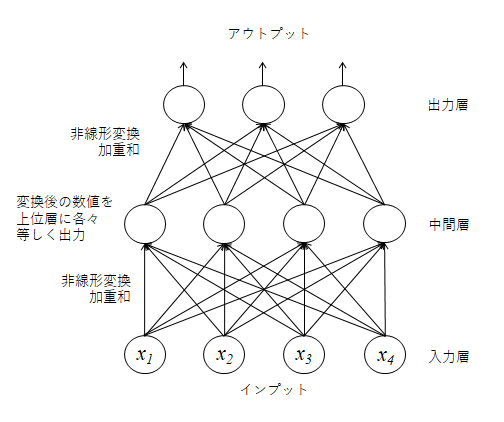2024年6月27日
エグゼクティブのための生成AI講座 その3 ―生成AIが文脈を理解するしくみ―
文章とは単語が並んだもの
シリーズその1では、1980年央に登場したAI第二世代の代表例であるニューラルネットワークがLLM(大規模言語モデル)の基本モデルになっていることを紹介した。ニューラルネットワークのみならず、コンピュータプログラムは、インプットデータやアウトプットデータとして数字を扱う。このため、自然言語をコンピュータで処理するためには言葉を数字化する工夫が必要となる。シリーズその2では、単語を数値化するベクトル化技術(分散表現技術)について概観した。
ところで、文章は単語の並びから成り立っており、その順番が文意や文脈を作り出している。数値化された単語をニューラルネットワークで扱う場合にも、単語の並びが重要となる。
しかし、当初開発されたニューラルネットワークは、インプットデータに順序性はなかった。順番をどう並べても、インプット値に対応するパラメータが変わるだけであり、並びの順番情報は活用されていなかった。
株価のような時系列データは並びが決定的に重要であり、順序を入れ替えると重要な情報を失ってしまう。ニューラルネットにおいて時系列データや文章のような順序性に意味があるデータを扱うには新たなモデルが必要であった。
1990年に登場したRNN(Recurrent Neural Network)では、データの順序情報をモデル内で扱えるような工夫がなされた。RNNは時系列データを扱えるモデルとして応用が進んだが、この時期はニューラルネットワークの学習能力の限界や問題点が判明した時期と重なり、その後、いわゆるAI冬の時代を迎えることになった。このためRNNモデルが注目される機会は減っていった。
ところが、自然言語処理(Natural Language Processing)の研究が進展するなかで、2000年代初頭にニューラルネットを自然言語処理に応用することで文章を生成するモデル(言語モデル)を作る試みが始まった。そして、2010年にはRNNを言語モデルに応用した研究が登場し、RNNは再び注目を集めることになった。
入出力の順序性
ニューラルネットワークの基本形は、次図に示したように各インプットの線形和(一定の比率をかけて足し合わせたもの)を非線形変換し、これを中間層の各要素とする。中間層は複数あり、各インプットは異なる比率で足し合わされ、各中間層に代入される。こうして作られた中間層の値を更に線形和・非線形変換してアウトプットデータとして出力する。
非線形変換の代表例はシグモイド関数であり、正負の様々な値を0~1の間の値に変換する関数である(次図)。これは、非線形性の導入により関数全体の表現力を高める役割を持つ。また、入力層から各中間層に来る加重和の値が大小様々に異なっていても、中間層の値を0~1の間に基準化する役割も有している。
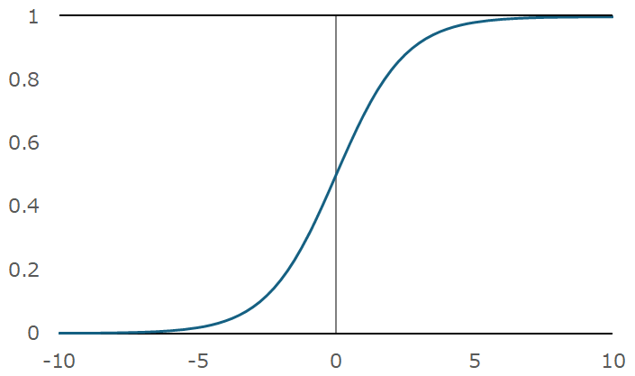
さて、インプットデータが時系列情報である場合、x1から右側に向かって、x2, x3, x4と順に並ぶ。ここで、x1とx2を入れ替えたとしても、中間層に向かって集計されていく際の加重ウエイトのパラメータが入れ替わるだけであり、順序が変化したことの影響を捉える手段がモデル側にない。
図示したようなニューラルネットの基本形では、入力層から中間層、出力層と一方向に情報が加工・集約されていくため、フィードフォワード・ニューラルネットワークと呼ばれる。初期のニューラル言語モデルはこれを利用していた。
単語の分散表現のアイディアは2000年に登場し、初期のニューラル言語モデルでは、単語をワンホットベクトルで表現し(その2の脚注2を参照)、これをインプットとしたうえでベクトル表現化はニューラルネットの内部で計算していた。前回解説した単語の分散表現の代表例であるword2vecはNNをより単純化した線形変換であり、NNの最下層に一体化して取り扱うことも可能である。前処理として単語のベクトル表現化を事前に行うようになったのは2013年に登場したword2vec以降である。NN本体に取り込んで一体表現したほうが非線形変換が入る分、表現力は高まる。しかし、実際は計算負荷や学習の難しさから、ベクトル化表現は別のモデルで行い、これをNNのインプットとするアプローチが後のLLMでも一般的となる。また、いったんベクトル化表現モデルを作ると様々なLLMに適用可能という汎用性がある点も、こうしたアプローチを可能とした。この背景には、ある問題領域(ドメイン)で学習したモデルを別の問題領域に転用することができるという転移学習能力をNNが有している点が関係している。
状態を記憶するRNN
当初のニューラル言語モデルでは、t番目の単語をアウトプットとして生成するために、直前のn個の単語をインプットデータとしていた。これは、単語や文脈の繋がりを反映させるために必要な処置であった。しかし、計算負荷の観点から扱える語彙数を絞る必要があり、またn個の単語の前後関係情報も活用されなかった。
これに対し、RNNでは過去にどのようなインプットがあったかという情報を累積・更新しながら引き継いでいく変数が導入された。これを隠れ状態ベクトルhtと呼ぶ。次図のように、一期前の隠れ状態ベクトルht-1と今期のインプットベクトルxtを合算することで、隠れ状態をインプットごとに更新していく。
この図では各インプットや一期前の隠れ状態から出ている矢印が一本で表現されているが、言葉を分散表現化することで一つの言葉が高次元ベクトルに変換されているため、実際には多くの数値を加重和として集約している。隠れ状態も高次元ベクトルであるため、こちらも加重和したうえで、インプット側と合算される。これにバイアス項(定数項)を加えたうえで非線形変換し、アウトプット層へ引き渡される(これがどう言語生成に繋がるのかは後述)。
なお、線形加重和や非線形変換のパラメータは、各t期において共通しており、インプット内容に応じて変化したりはしない。言い換えると、どのようなインプットや隠れ状態ベクトルに対しても共通して対応する高い汎用性を持つ。
隠れ状態ベクトルは、過去のインプットを順次集約して積み重ねていったものであるため、言葉の並びが作り出す意味・文脈情報が埋め込まれている。こうしたRNNの仕組みにより、文章に対応する能力が高まった。
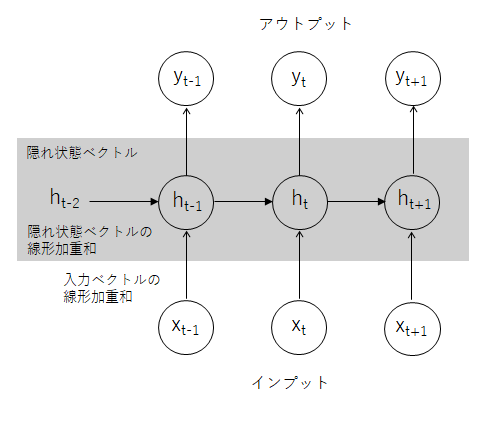
RNNもディープNN化が可能
図では、隠れ状態ベクトルは1階層となっているが、複数の隠れ状態ベクトルを階層構造として導入することができる。これは、ディープニューラルネットワークのアプローチと同様である。すなわち、基本形のフィードフォワードニューラルネットワークでは、中間層を複数階層に積み上げる(ディープにする)ことで、インプットとアウトプットの間にある複雑な情報構造を捉える能力を高めることができる。言い換えると、インプットをアウトプットに変換する関数として、より複雑で高性能なものを作り出すことができる。これがディープラーニングモデルの特徴となっている。RNNの隠れ層にも同じコンセプトを適用し、深く階層化することで能力向上を図ることができる。
数学的な解析により、ディープラーニングモデルが高い性能を持つ理由が明らかになっている。まず、中間層のうち低層部分において、インプット情報から特徴量(データに内在するパターン性)を中間層の各要素別に集約する。上層部では、得られた様々な特徴量の組み合わせによってアウトプットを表現している。こうした仕組みにより関数としての性能(近似精度)を高めている。ただし、こうした原理が数学的に解析されているのは、モデルが複雑でなく極端にディープでないものに限られており、それ以外のものは上手く機能する理由が未だに判っておらず、研究が続いている。
ディープラーニングモデルは膨大なパラメータを持つ。その推計法の基本的な考え方は1980年代央に考案されたAI第二世代モデルから変わっていない。教師データ(正解を示したアウトプットデータ)にフィットするよう膨大なパラメータ群を誤差逆伝播法により推計する。このパラメータ推計のことを学習と呼んでいる。これは、正解を示す教師データにアウトプットが近づくようニューラルネットを学習させるという考え方から由来している。その際に、アウトプットの誤差から中間層のパラメータを、次にインプット層のパラメータを逆方向に修正していくため、誤差逆伝播法と呼ばれる。誤差を最小化する過程では段階的にパラメータ修正を繰り返す方法がとられており、微分の考え方を用いた再急降下法という手法が適用される。
ニューラル言語モデルは確率モデル
RNNが言語を生成する仕組みを理解するために、まず、一般的なニューラル言語モデルの言語生成原理から説明する。LLMの問題点としてハルシネーション(幻覚、もっともらしい嘘)が指摘されているが、確率モデルとしてのニューラル言語モデルの成り立ちを理解すると、いわゆるハルシネーションの発生は必至であることが判る。こうしたLLMの原理を理解しておくと実務への応用時に使い道を誤るという失敗が回避しやすくなる。さらには、GPTのような汎用LLMがどのような限界を抱え、その課題をどのように乗り越えているかを知り、実装に活かしていくかを学ぶ上でも有益である(今後のシリーズで紹介予定)。
言語モデルで文章を生成する場合、以下のような手順が一般的である。ある単語の並び、例えば、{日本/の/首都/は/}があったとする。次にくる単語を予想すると、「東京」が最有力候補であろう。もちろん、「暑い」でもよいし、「京都/だった」が続くこともありうる。しかし、蓋然性が最も高いのは東京であろう。
確率言語モデルも同様な発想に基づく。条件付確率P(東京|{日本/の/首都/は/})を求めて、東京以外の他の全ての単語候補と比較し、一番確率が高いものを選択して、これまでの文章に付け足す。これを次々に繰り返すことで文章が生成されていく。
広辞苑の収録数は約7万語である。それより遥かに多くの単語について、確率計算を行うのは膨大な計算負荷が生じる。このため、様々な計算節約手法が考案されているが、文章生成の原理は上述の通りである。最も高い条件確率を示した単語を選択するか、多少のゆらぎをいれるかなどバリエーションが選択・程度調整可能な仕組みが取り入れられている。
こうしたLLMの言語生成の仕組みは、その用途ほどには知られていない。2022年にChatGPTの登場によりLLMに社会的な注目が集まったが、当時、LLMを検索サービスのように誤用することが広範に生じた。LLMは学習用の膨大なコーパスに存在している単語間の登場のパターン性を学習し、次の単語を確率的に繋ぎあわせることで文章を生成しているにすぎない。にもかかわらず、整理された知識がLLMから引き出せるかのように利用され、結果、ハルシネーションを起こす点が問題視された。
その後、LLMが高度化・巨大化し、学習のためのデータセットも膨大なものとなったため、あたかもLLMが膨大な知識を保有しているかのように見える度合いが格段に高まった。もちろん、単語間の関連性や登場順に関するパターン性が極めて精緻に把握されれば、LLMに知識が蓄えられたと捉えることもできる。このため、上述のような誤解が解消されにくい状態が続いており、これがLLMの用途の適切な選択に悪影響を及ぼしている面がある。
RNNの応用バリエーション
前出のRNNの解説図では、インプットとアウトプットが一対一に対応していたが、異なる設計も可能である。代表的な設計例を次図に示した。一番左は、インプットとアウトプットが1対1に対応している事例である。最もシンプルなこのケースでは、中間層があるものの、その内部の隠れ状態ベクトルが横方向(時間展開方向)に引き継がれていないため、RNNとはいえない。他事例の説明のための基本形として取り上げたものである。
しかし、このシンプルなケースも用途は多々あり、例えば、画像認識や分類・識別問題がこれに相当する。1つの画像をインプットとし、それが何を示しているかをアウトプットとした画像の分類・識別の事例である。
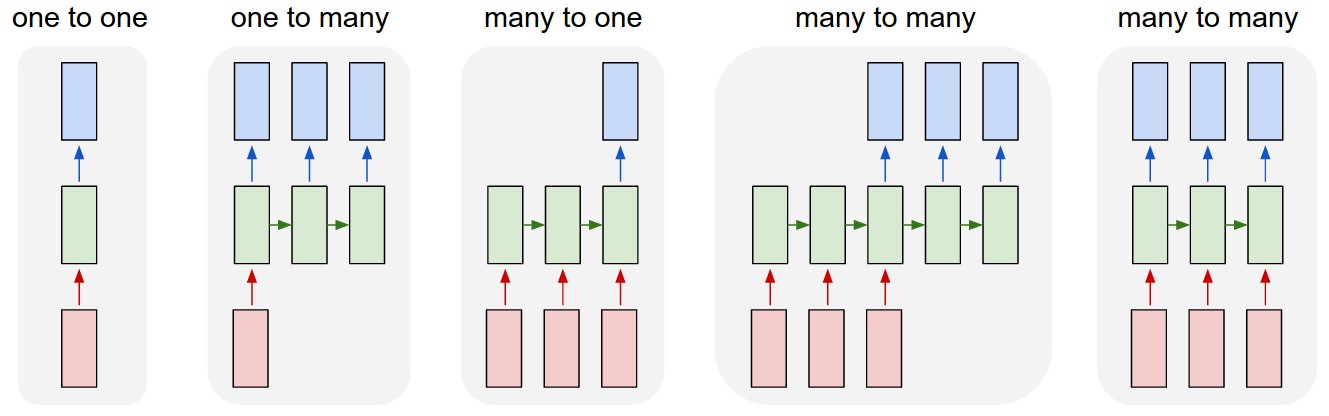
出典)Andrej Karpathy, “The Unreasonable Effectiveness of Recurrent Neural Networks,” May 2015.
左から2番目は、画像からの文章生成事例である。文章を単語の逐次生成によって作っていくため、アウトプットが順次作成されている。一つの画像インプットから最初の単語を生成し、隠れ状態ベクトルを更新しながら、その単語が生成されたもとでの次の単語を選択していく手続きをとる。
3番目は、文章からの内容分類などが相当する。アウトプットは内容に関する複数の候補であり、逐次入力されるインプットを最後まで受けたうえで、アウトプットが生成される。例えば、この文書のトピックは何か(国際政治、経済、スポーツ、芸能、金融市場等)を識別させる問題である。企業の決算報告を読み込んだうえで、今後の株価が、上がる・下がる・横ばいという離散選択肢を選ばせる問題もこれに相当する。
4番目は翻訳が典型例である。日本語の文章をインプットとし、最後まで読み込んだところで、英語の文章を順次生成していくケースに相当する。5番目は、同時通訳やビデオ画像へのキャプション文書生成などに相当する。4番目との違いは、インプットの読み込みを最後まで待たずに、順次アウトプットを生成していく点である。
seq2seq:エンコーダー・デコーダー
上記のようにRNNの応用モデル形が広がるなか、2014年にRNNを2つセットで利用するseq2seqモデルが提案され、機械翻訳などへの応用が加速した(正確にはRNNの発展形であるLSTM<後述>を利用している)。
seq2seqでは、一つのRNNでインプットとアウトプットを対応させるのではなく、前半のRNNでインプット情報を隠れ状態ベクトルに集約させ、これを後半のRNNの隠れ状態ベクトルの初期値として引き渡し、アウトプットを順次生成していく手法である。次図のように、後半のRNNのインプットには、一期前のアウトプットが用いられている。日英翻訳の場合、日本語文章を読み取った後、生成された英単語が逐次的に翌期のインプットとなる。
単語の並びとしての文章内容を高次元の固定ベクトル(ここでは隠れ状態ベクトルht)に変換することを、エンコーディング(符号化)と呼び、これを順次文章に復元することをデコーディング(復号化)と呼ぶ。2つのRNNをエンコーディングとデコーディングに特化させて使うアプローチであり、のちにLLMの性能を劇的に改善させたTransformerモデルも、エンコーダー・デコーダーモデルとして作成されている。
エンコーダー部分はアウトプットを持たず、デコーダー部分のアウトプットを翻訳結果とすることで2つのRNNがセットで学習されることになる。通常のRNNでは各期の線形加重和や非線形変換のパラメータは共通となっているが、seq2seqではエンコーダー部とデコーダー部のRNNでパラメータが異なる分、モデルの自由度が高まり、学習性能も向上する。
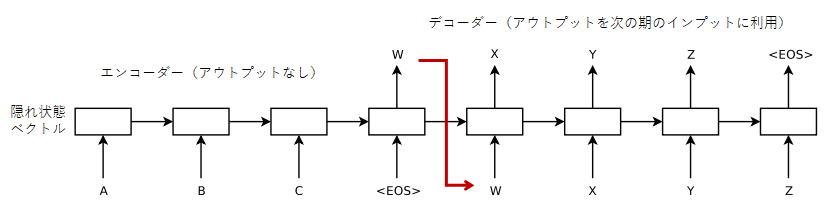
出典)Ilya Sutskever et.al, “Sequence to Sequence Learning with Neural Networks,” 2014.
注)EOSは文章の終了を示す。オリジナル論文の図表に筆者が加筆。
なお、seq2seqモデルの用途は機械翻訳に限らない。文章を与えて要約文を返す、質問を与えて回答を返す、対話を与えて対話を返す、文章を与えて文法誤り修正後の文章を返す、口語文章を与えてビジネス文章に変換して返すなど、文字系列を異なる文字系列に変換する様々な用途がある。
seq2seqモデルは、言葉の意味からすると、文章のような系列インプットを系列アウトプットに変換するモデルを指すことになる。しかし、エンコーダー・デコーダーという仕組みを取り込んだ研究によってseq2seqという名称が定着したため、エンコーダー・デコーダーモデルを含意することが一般的である。ほぼ同時期に同様なモデルを開発した研究論文は、seq2seqではなくエンコーダー・デコーダーモデルという呼称を用いている。
RNNの2つの課題
こうして登場から10数年の時をおいて、時系列データから自然言語処理に用途が拡大したRNNだが、モデルの構造上、2つの課題を抱えていた。一つは、隠れ状態ベクトルのアップデイトをどれほど強く行うか、すなわち、新しいインプットの情報を強く反映させるか、それとも過去のインプット情報を長く保有させるかというトレードオフである。
前者の場合、過去の情報が損なわれやすく、文脈を長く保持しておくことができない。逆に後者の場合、新しい単語がもたらす文章内容の展開について行けなくなるという問題がある。適切な単語の選択は直前の単語の影響を強く受けるため、直前や近い位置のインプット情報を重視せざるをえない。このため、RNNでは遠く離れた単語や文脈をうけて次の単語を適切に選択することが難しかった。言い換えると、隠れ状態ベクトルにおいて長期記憶を保持することが困難であった。
もう一つの問題は、学習に誤差逆伝播法(の応用系)を適用する際に、計算が不安定化もしくは進行しなくなり精度が上がらなくなるという学習時の難点であった。
RNNが自然言語処理に適用される以前から、こうした問題は認知されており、解決する方法が考案されてきた。1990年代央から後半にかけて登場・改善されてきたLSTM(Long Short Term Memory)が代表例である。2010年代にはRNNと同様に自然言語処理への適用が進展した。その後、LSTMの構造をよりシンプルにし計算・学習効率を高めたGRU(Gated Recurrent Unit)も考案されている。その4では、LSTMやGRUの仕組みについて解説する。
なお、RNNやLSTMは隠れ状態が入れ子上になって時間展開しており、誤差逆伝播法では計算負荷が大きくなる問題も別途、存在していた。これは、Transformerモデルに組み込まれたAttention機構で解決された。同モデルは生成AIの性能を劇的に改善させた点が最大の特徴であり、これによりBERTやGPTなどに代表されるLLM時代が2010年代末に到来する。大規模言語モデル(LLM)という言葉は、Transformerモデルの登場とそのモデル規模拡大による著しい性能拡大によって登場し、普及していくことになる。